春の夢 宮本輝 文春文庫(1988年刊行)
大阪の中でも交通の便の悪い、さびれた地区。家賃7500円の、かび臭い部屋。壁と壁の間に露出している四寸角の柱。そこに、5センチ程の釘を打ち込む、22歳の主人公。
その釘で意図せず貫いてしまった蜥蜴(トカゲ)。主人公はこの蜥蜴をキンと呼んで、生かしています。
まだ、携帯電話というものが、世間で使われだす前の時代。そんなある年の春、物語は始まります。主人公の井領哲之は大学の四回生。
その哲之の引越しは、父親の残した借金を執拗に取り立てる、やくざ者から逃れるためのものでした。
耳で聞く、読書はいかが?
総評
人生の中には、自分だけの力ではどうともならない事象や、時期、というものがあります。まさに、哲之が遭遇している事態はそのようなものでした。
父親の残した借金は、五枚の手形。そのうちの三枚は、相手がこちらの窮状をみかねて破棄してくれました。しかしあとの二枚の手形の取り立ては執拗で、一つは、54万円を、それでも月賦で払う約束となります。哲之が自分で交渉し、就職してから払う段取りとなっていました。もう一枚の、手形ブローカーに渡った32万3千円の六ヶ月手形が問題でした。
「話し合いとか、こちらの事情など通用しない相手で、夜中に訪れて、明け方近くまで、すごんでみせたり、優しく哀願したり、あの手この手で三ヶ月間、哲之と母の住む家に通ってきたのである。」
本来、このような負債は、哲之も母も負う必要はありません。やくざな取り立て方も、現在では法が取締るでしょう。しかし、まだ昭和の4、50年代。そのような取り立ては、横行していたでしょう。法律云々は、例え知っていたとしても、現実の罵声や暴力を目の当たりにすれば、闘う気力など持てないことは、想像できます。一度闘うなら、報復や長期的な仕返しも想定しなくてはならないでしょう。
そして、冒頭の、引越しの場面となるのです。父の死からの目まぐるしかった一年は、物語の中ではすでに、哲之の過去の一部となっています。このような経験が、彼にある種の諦念と人を見る目の怜悧さを与えました。
このような環境に置かれて、自暴自棄になり、転落の一途を辿る可能性も読者としては想像してしまい、怖いものみたさと、祈るように思う気持ちを持ちながら、読み進むことになります。
哲之という人物は、しかし、言いしれない底力を人生に対し持っています。それは冷静さ、人生をしっかり自分でコントロールしようと踏み止まる強さでした。
彼は、ホテルのボーイとしてのアルバイトを始め、大学の講義はしたたかに代返を頼み、この事態が起こる前からの恋人に想いを寄せ続けます。彼をそうさせたのは、若さなのでしょうか。それまで注がれた親からの愛情でしょうか。あるいは、ある種の「怒り」かもしれません。
この世に、選んできたわけではないのに、結びつけられ生きている、自分。
人が作ったルールの中で、もがく自分。
人の作ったルールを超えてなお存在する、自然の摂理の中にいる、自分。
貫かれてなお、生きている。貫いた相手に水をもらい、餌をもらい、愛撫されて生きている。貫いてしまった蜥蜴に、自分を重ね、恋人を重ね、出会う人々を重ね、哲之は、蜥蜴の釘を抜く日のことを考えています。
物語は1980年代の大阪、京都を舞台に進みます。携帯電話が一般的ではなかった時代、固定電話の前で恋人からの電話を待ったり、電話をかけるために小銭を作ったり、懐かしく思い出す世代の方も多いでしょう。「女の人生は男しだい」といったセリフだとか、恋敵との直接対決だとかは、やはり時代を感じます。しかし、40年ほど前、貧しさはさほど特殊ではなく、一種バイタリティーを生んでいたであろう時代の空気が、本書にみなぎっています。
物語の中で、私が特に、気になった人物について少し、ご紹介します。
京都の老婦人
物語には、哲之と恋人の陽子が、ドイツからきたという老夫婦を京都で案内するくだりが出てきます。ここで登場する、不思議な一人の女性、沢村千代乃。
ドイツの老夫婦は死に場所を探して「東洋のどこか静かな限りなく美しい場所で死のう」とやってきていたのですが、そうとは知らず、哲之と陽子は知り合いであった老婦人、沢村千代乃の家に老夫婦を伴います。千代乃の家は京都の修学院離宮の竹林の中に建ち、二千三百坪ある庭には茶室もあります。美しい庭を夫婦で堪能できるよう、茶室を夫婦に案内しますが、夫婦にとっては、探し求めていた最期の場所にたどり着いた形になっていました。哲之らの機転で、すんでのところで死ねなかった夫婦。そのふたりに、千代乃はお茶を点てて振る舞います。
「茶は、生死を覗き見る儀式だと思っているの。茶もまた、あなた方が信じていらっしゃる神と同じかもしれない。私は茶も宗教だと思っています。茶室にいるときは、亭主も客も死。茶室から出たら生。だからここから出たら、いやでも生きなきゃいけません。」
また哲之たちにも
「二十歳のときから茶を習って、もう六十年以上も私は茶の何を見て来たんだろうって考えたんです。そのときふいに茶が緑の毒薬に見えたんですよ。毒薬というより、死そのものに見えたと言ったほうがいいかもしれませんねェ。そこに死があって、私はその傍でいま生きている。(略)私、絶対にそうに違いないって思ったの。二年前の冬の夜明けにね。目の前の、赤茶碗の中の死を見たとき、本気でそう思ったの。だから私は茶室でお昼寝をするんです。眠っている私は死。目覚めたら生。どちらも同じ私。」
そんな風に語るのです。
しかし、老夫婦のために、親族への連絡をとったり、その晩泊めてやったりと、行動をしてやりながらふと
「おふたかたは、ここでは死ねなかったけど、きっとどこかで目的を遂げるでしょう。お別れのお茶ね」
とももらします。
この一件からしばらくして訪れた、沢村千代乃の最期を、しかし作者は、穏やかには描きませんでした。
鳥肌が立ち、思わず声をあげそうになった。そこに見たのは、色白で品位にあふれた泰然自若たる生前の沢村千代乃ではなく、肌の黒ずんだ、異様なほど苦悶に歪んだ、醜悪な死に顔であった。右の目はきつく閉じられ、左の目は大きくみひらかれていた。
作者は陽子のセリフにこうしるしています。
「ずっと前に、何かのフランス映画で、あいつは人殺し以外ならなんでもやって来た女だっていうセリフがあったのを覚えているの。沢村のおばあさまと初めて逢うたとき、私、そのセリフを思い出したの。」
「目と顔の動きがちぐはぐやったもん。気味が悪いくらい。なんて言うたらええのかなァ。ねえ、わかるでしょう?ひとりの人が、何枚ものお面をかぶって、取っ換え引っ換えしてる感じ。顔は変わっても目ェだけは一緒。」
顔というのは、不思議なものです。人相学というものがありますが、確かに顔や目、姿勢や歩き方には、「その人」が現れます。善悪の基準としてというより、どうしようもなく、「その人らしさ」が現れるというかんじでしょうか。私自身も、近しい人や気を付けている人であれば、足音でもその人、と分かるようになりました。
人相学自体は、そこから自分にとっての良い人、悪い人、を見分ける便宜上、善悪や性格を定義付けていくのでしょう。大抵の人にとって、善人であるか、悪人であるかは、自分にとって有益であるか、害悪であるか、に置き換えられるでしょうから、生存する上で大事な情報です。
この情報、しかし、平和に平和に生きてこられた人では、読み解くのが苦手な人も多いように思います。あるいは、人など見る余裕のない人も気が付かないかもしれません。
この物語の主人公は、過酷な経験からか、人を見抜く能力に長けています。その恋人の、陽子もしかり。
ふたりにとっては、千代乃は年の離れた友人であり、深い言葉ともてなしを提供してくれた人のはずです。しかし、二人はかすかな違和感を感じていました。
そんな二人にも、見切らせないまでに仮面をつけていた老婦人、沢村千代乃。彼女が何かを取り繕っていたのか、何かを怖れ、善行を行っていたのか。完全なる悪人であれば、むしろ葛藤などしないでしょうし、自分に利のないもてなしは、しないでしょう。しかし、彼女は客をもてなし、生きるよう諭し、ことさら泰然自若として振る舞います。彼女がそうした姿を見せたかった相手は、本当は誰だったのでしょう。
不思議なこの人の残像は物語を読み終わっても思考を捉えて離しません。
仕事場で出会う男、磯貝
磯貝は、哲之がバイトを始めたホテルで、ボーイを束ねる社員です。
ボーイとしての仕事をまず最初に教えたのが彼でした。無責任なバイトを嫌う彼の印象は、最初冷たいものとして哲之には感じられました。しかし、しばらくホテルで働いていくうちに、磯貝が過重の仕事をすると倒れること、それは心臓に病を抱えているからであることを知ります。さらに、職場の人間から彼の過酷な来歴をも聞かされた哲之。
職場では、弱みを見せたくない相手もおり、なかなか自分のことは語らない磯貝が、ついに自身の病について話したとき、哲之は、自分のこととして、彼の痛みを受け取る感覚を覚えます。
何とか、励まそうとするうちに、自分の置かれている状況を語り、あの、柱に釘で貫かれた蜥蜴の話もしていました。その蜥蜴の話に、異様に興味を示す、磯貝。家まで、見に来ると言い出します。
そうして、せまい六畳に、男二人での夜、磯貝は蜥蜴を異様な眼差しで見ながら、語り出します。
「俺、小さい時から心臓が悪かったから、いつ死ぬかもわからん、五分後に死ぬかも知れんし、あしたの朝に死ぬかもしれん。そんなことばっかり考えて生きてきたんや」
「もしも、また生まれてきても、俺はやっぱり心臓の病気を持って生まれてくると思う。」
「借金をかかえたまま眠っても、目が醒めたら借金がなくなってたなんてことはあらへん。それとおんなじことのような気がするねん。そやから、自殺したって、そんなこと無意味や。自殺のしがいないって考えだしてから、どうしてええんかわからんようになってしもた。おい、どうしたらええと思う?」
「死んだら、それで終わりや。」そういう哲之に、磯貝は畳みかけます。
「俺は、絶対、そんなふうには考えられへんのや。(略)結果の前には、必ずその原因があるんや。(略)なんで人間は、生まれながらに差がついてるんや。ある人は金持ちの家に生まれる。ある人は貧乏な家に生まれる。ある人は五体満足に生まれる。ある人は不具で生まれる。(略)人間は覚えてないだけで、この世以外の人生を、以前に確かに経験してるはずや。それでいろんな借金をかかえて死んだんや。それから眠って目を覚ますみたいに、また生まれてきた。そやけど借金は消えてない」
「釘を抜いてほしいのはおれのほうや。」
そして、おたがいに、「精神科に行け」と言いつつ、その夜をすごします。磯貝の、この仏教の世界観ともいえる死生観は、我々もちらと、脳裏に持っている思想でもあり、作者の当時の死生観でもあるでしょう。
逃れられない、痛みや苦悩を、その心に去来するものを含めて共有したふたり。このふたりのしていた会話や、行動を「傷のなめ合い」などという言葉にはできません。
深い釘を穿たれて、繰り返す運命に怯える心と体を引きずって、なんとかこの生に食らいついている。そんな時を、共有する人がいるのだということ。
初めて出会ったときにみた「顔」。そしてふたりの間に時が流れて現れた「顔」。
この磯貝という男もまた、この物語を超えて、読者の心に住み着いてしまいます。
最後に
哲之が、一人暮らしを始めるところから始まる、物語。春に始まり、翌年の春を迎える頃、物語は終わります。蜥蜴の背に空いた穴から、すかして見ていたような哲之の一年は、夢から覚めるように、終わっていきます。
湿度と、退廃と、諦念と。しかし土の中から湧き出すような命のエネルギー。そういったものを連想させるこの物語は、春という季節の持つ空気そのものでした。
皆様も、春の宵にぜひ読んでみてください。
今回は京都を連想するというよりは、大阪の貧しい一角を想起させる小説の紹介となりました。しかし、京都にしても、大阪にしても、まばゆい光の集まる街という場所では、影もまた色濃く深く伸びるもの。小さな茶室の中、六畳の借家の中、すべてに生と死は詰まっています。
街歩きをする際は、街にある、美しいもの、猥雑なもの、生きるもの、死すもの、様々なものに焦点を当ててみてください。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
【おすすめ】
京都の和雑貨、ギフトにどうぞ
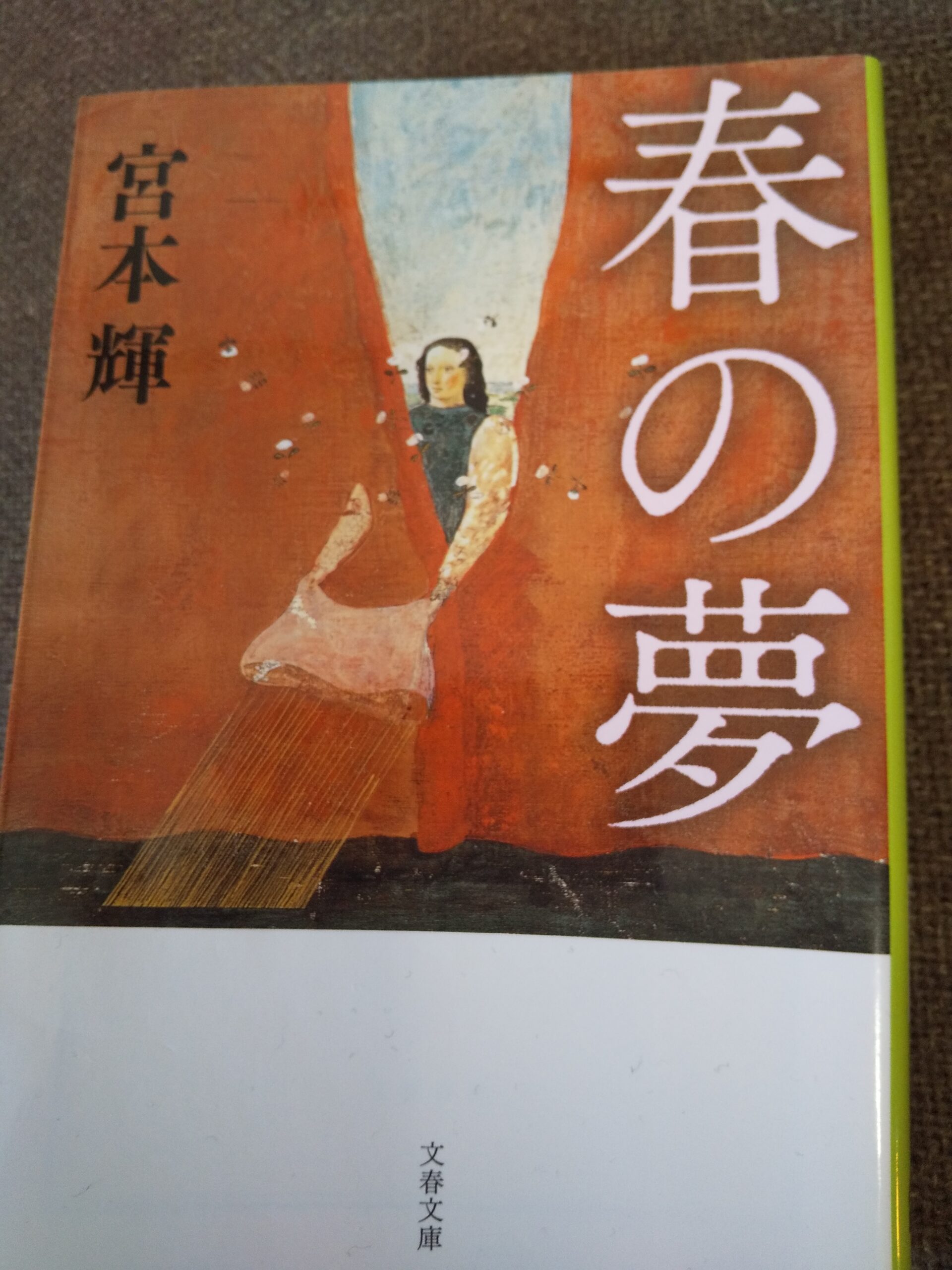


コメント